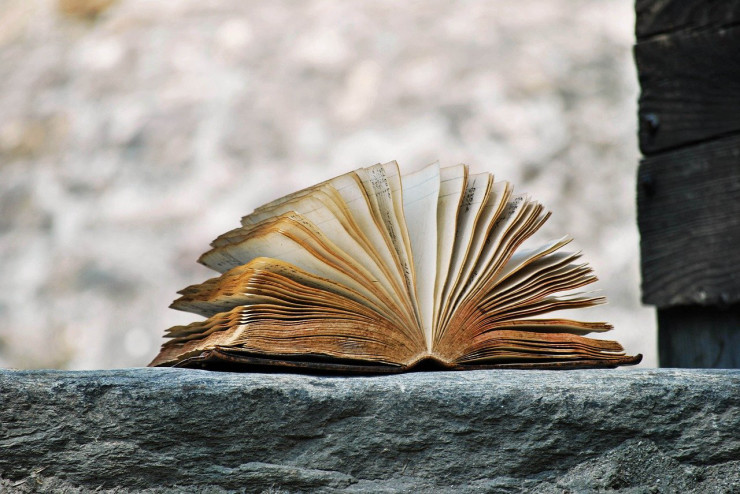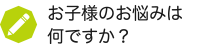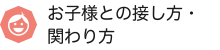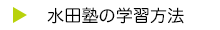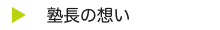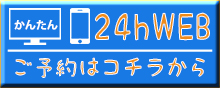1学期末試験も終わって、結果も戻ってきてると思います。今子どもたちは、学校の「訂正ノート」に追われてるのではないでしょうか?そして、今回の試験で出た結果を踏まえて、今後どうしていこうかなぁと今一度考える時期でもあります。また、新しい環境に慣れるまで塾を控えていた方や、長年通っているけど全然成績が伸びない方などはこの夏休みの過ごし方で大きく変化しますので、いい機会になるのかなと思います。
そして、このタイミングでよく出てくるワードが【夏期講習】ですよね。
ただ、みなさんこの【夏期講習】に関していろいろ間違えてるんじゃないかなぁと言うことがあるので、ここで少しお伝えしておこうと思います。
ここでは、注意してもらいたい順に記載しておきます。
(※あくまで私個人の意見ですので、絶対ではありませんし、他の考え方もあっていいと思います。)
1.無駄に多くの教科を受講する
これは、無駄な夏期講習の最たる例ですね。「夏休み後に他塾から転塾してこられる方」や、「長年塾に通っているけど成績が上がらないとご相談にこられる方」、「講習の目的意識がなく塾に言われるがままに講習を受講している方」にとても多いです。
私の個人的印象では、大手の個別指導塾で受講されている夏期講習に多いですね。一つの事例を挙げておきます。
昨年秋に大手個別指導塾から転塾してきたA君の夏期講習プログラムは、【週4日で、数英国理を週1回受講】と言う恐ろしい内容でした。聞こえはすごく良いんですけどね・・・『4教科も夏期講習受ける』って!
でも実際よく考えてくださいね!各教科週1回ってことは、夏休み全体で1教科の学習時間が多くても5~6回ですよ。たったこれだけの回数で1年間、もしくは2年間の内容の復習が出来ると思いますか?さらに、苦手な単元を復習するとするならば、なおさらこの時間数で全て復習できると思いますか?私は笑うことしかできません。(笑)もしそれが可能なら、高校受験の勉強は、中3の夏休み明けからしても十分に間に合いますよ(笑)
つまり、あれもこれもと手を出しても、何の結果も得られないという言ことです。たかが1ヶ月強の休みですよ。今まで学習した1・2年間の内容が全て復習できると思っていること自体おかしいのです。出来ない内容があって当然である!だからこと、「何をするのか」と言う目的が重要になります。
たかが1ヶ月強の夏休みです。出来ることを絞って学習し、出来ないことはいつまでにどのように対策するかを考えることが大切なんです。くれぐれも、「全教科~」なんて聞こえの良さに惑わされて、無駄な夏期講習にならないようにしてくださいね。
2.夏期講習を受講したこと(受講させたこと)に満足
これは保護者の方に多い事例です。うちに転塾してきた方も、「夏期講習は受けてたんですけどね。全然成績が上がらないんです。」とよく言われます。ただ、「どういった内容を受講されたのですか?」と聞くと、「よくわかりません。」や「塾の先生に言われたまま」等、結果的に何のために受講したのか、どうなりたいから受講したのかが全く明確になっていないことがほとんどです。
「とりあえず夏期講習を受講した」は、お金をドブに捨てるようなものです。
「外食に行って、食べたいものではないが店員さんが出してきたらかとりあえず出したので食べた」なんてことありますか?さらにそれに対してお金を払うなんてこと。自分が〇〇を食べたいから注文して、それに対してお金を払って満足しますよね!
夏期講習だって同じだと思いませんか?あなたがどうなりたいのか、何が出来るようになりたいのかを持たなくては意味ないんです。そのなりたい自分になるために何を・いつまでに・どのようにすればいいかを考え指導するのが塾の役割です。塾の言いなりになっちゃダメなんです。あくまで、勉強を進める主人公はあなたであって、あなたの意思があって初めて周りのサポートがスタートするんですよ。
3.費用や回数だけで決める
これに関しては、やむを得ない状況もあるかもしれませんね。また、単純にお金をかければ、授業をたくさん受講すればいいってことでもないでしょう。
ただ私が言いたいのは、楽観的に「こんなにたくさんしたくないなぁ」とか「もっと費用抑えて減らしてください」など、そこだけに着目しないで欲しいと言うことです。
なりたい自分の目標値が高ければ高いほど、当然やるべきことは増えます。一般的に中1生よりも中3受験生の方が講習受講回数が多くなることが証明しています。
〇〇高校に行きたい!
↓
じゃぁ、この夏にはここまでは出来る状態を作っていないと間に合わない!
↓
その為にはこれだけの授業が必要だ!
となれば、出来る限り受講することをお勧めします。
ただしどうしても出来ないこともあると思いますから、その時は再度学習内容を検討して計画を作ればいいと思います。
4.夏期講習だけで学習が完結する学習計画
これは結構落とし穴的な部分ですね。とくに受験生にとっては。
小学校、とくに中学校の学習は今まで習ったことが全て繋がってきます。つまり夏期講習だけで学習が終わることはないのです。当然学校も2学期3学期と続きますしね。
よくある勘違いが、「夏休みに中1と中2の復習をした」と得意げに話す子どもたちです。復習ができたと自信を持つことはとても大事ですが、そこで終わりじゃないんです。その復習を活かすのは7ヶ月後の受験当日です。では、夏休みだけの復習で7ヶ月間記憶が残っているでしょうか?(笑)当然むりですよね。
つまり重要なのは、夏期講習で復習や苦手科目の学習をしたならば、それを今後どのように忘れないようにしていくかまで考えておく必要があるのです。
「夏期講習はよく頑張ってました」と言う言葉だけで安心しないようにしてくださいね。ここで完結する勉強なんて、どの学年でもありませんから。
いろいろとお伝えしましたが、本質としては意味のある夏期講習を是非受講していただきたいという思いです。
せっかくお金を出すのであれば、本当に身になるものをするべきです。
自己満足の世界で終わることの無いよう、多くの方が「受講してよかったぁ」と思える夏期講習に出会えるといいなと思ってます。
いよいよ1学期の期末試験が近づいていますね。
近隣の中学校の多くは、6月24日~6月28日の週に期末試験があります。つまり、1週間前の6月17日には試験範囲の発表になるわけです。
ただここで一つ大きな問題が!それは総体ですね。部活によっても異なりますが、おおくが6月10日~6月14日の試験発表の前の1週間で行われます。そうなると、やはりまずは部活に集中して、部活が終わってからテスト勉強に・・・と言う人がほとんどになるんです。
例年、それで1学期末の試験の結果が悪くて、そこから塾を検討される方が多くいらっしゃるのも事実です。私としては悔しいんですよね。この1回の試験の結果も、高校入試の内申点に大きく影響しますし、2学期以降の学習にも大きく影響してくるんです。全力で出来る限りの対策をしてからテストは受けないと意味がないと考えています。
もちろん、部活も手を抜いてはいけませんよ!中3生にとっては、3年間頑張ってきた最後の集大成になるわけですからね。
だからこそ、水田塾ではGW明けからこの期末試験を意識した対策を実施していたのです。(5月中は生徒もダルそうにしてましたけど)なので、今では多くの生徒が主要5教科のうち1または2教科はすでに80点前後の点数がとれる状態を作ることが出来ているんです。これから試験までの残り期間は、理科社会の勉強と、英語数学の自身の苦手な問題だけに徹底して学習していきます。
ある生徒(中3)の学習の流れを一例で挙げておきますね。この生徒は数学が1番マシ(得意と言うわけではない)で、英語・理科は嫌いと言う生徒です。
【数学】
5月中に予想される1学期末試験の範囲の学習が終了→現在は毎回テスト形式で予想試験範囲の問題を実施
【英語】
5月中に予想試験範囲の英単語と例文のみを反復して暗記→現在は教科書内容の問題を必ず毎日解く(量は日によって変動)
【理科】
5月中にイオンを一通り学習→苦手意識が大きいため、現在はイオンの学習を2週目(9日終了予定)→以降テスト形式
【社会】
5月中に歴史を最後まで一通り学習→6月9日には予想試験範囲の学習2回目が終了→10日以降3回目実施→発表後テスト形式
【国語】
時間がないため特に何もしていない→試験発表後、国語の時間を少し多めに確保して対策
といった感じですね。大まかな内容ですが、こうした計画のもと実施しています。
「こんなに無理ーーー」と思われるかもしれませんが、この生徒も部活はしてますし、部活が終わってからやってる内容です。夜は体調管理も含めて、必ずその日のうちに布団に入るようにしてますし、土日は練習試合などの1日錬も通常通りやってますよ。
みんな、やる前から「出来ない、無理、しんどい」って決めてるから出来ないんですよ。しっかりとした計画のもと、何のためにそれをするのかさえ分かっていれば誰でも出来るんですよ!
現にこの生徒も、3年生になって「高校どうしよう、マジでヤバいっす」が口癖でした。なので、「期末で結果だして、内申点まずはあげるしかないんじゃない?」と言ったところ、「じゃあ」ってことで始めましたからね。
ようは、「やらずに逃げるな!」「どうせ‟やらない”という選択をするならやってからにしろ」ってことです!
何にしても、早く始めないと絶対に間に合いませんからね!
試験発表が出てから!なんてのは愚の骨頂ですよ!
大人でもよくありますよねぇ。
私自身もそうですが、お父さんお母さんもありませんか?
例えばTVで凄い先生の健康の話で、日常でこんなことを取り組むとすごくいいという話を聞いて、「おお、なるほど!簡単だしすごくいいなぁ!」とテンション上がって感動したけれど、一週間経っても一ヶ月経っても結局何にも変わっていないってこと。
本当はすぐその話を聞いて、その内容を自身の行動に活かさねばならないのに、聞いただけで満足しちゃうんですよね。
僕も営業時代や教員時代含めて、いろんな人の素晴らしい話を聞いたり、本で読んだり、TVで見たりしてきました。そして、その内容も覚えているもの忘れているもの多々あります。
今思い返してみて「これはよかった!」と思えるのは、やっぱりその後即行動に移したことばかりなんですよね。そして、思い返すことが出来るのも、自分が実行したことばかりなんですよね。ここで当たり前の気づきを、自戒を込めて再度自覚しましょう。
行動するってやっぱり大事。
そう、生徒諸君、あなたたちも一緒なんですよ。学校や塾の授業でも、私たち大人と同じことが起こり得るんです。
どんなにいい説明でも、聞いただけでは自身の成長には直結しないんですよね。すぐ忘れちゃうしね。
・問題を解いたら見直しします。→実際の問題を見直す具体的方法がわからないため何も行動しない
・なるほど「わかったぁ!」→これ自体はいいことですが、点数が伸びない生徒の90%がここで終わっている
・間違えた問題は赤で直す→答えを写して自己満足!写すという行為だけなら学んでいない幼稚園児でもできます
成長に結びつけたいのなら、説明を聞いただけで満足せずに、その内容を自分自身でかみ砕いて理解しながら、アウトプットすることです。アウトプット、つまり自分の外側に出すということが最も重要で必須になるんです。
・有名女優のドラマを見たら、あなたは有名女優になれますか?
・メッシやエムバペの試合を見たら、あなたはメッシやエムバペになれますか?
・大谷翔平さんの試合を見たら、あなたは大谷翔平さんになれますか?
・岸田総理の話を聞いたら、あなたは内閣総理大臣になれますか?
・「かまいたち」のコントを見たら、あたなは人気お笑い芸になれますか?
答えは誰にでもわかりますよね。当然NOですよね!
説明を見たり聞いたりした後が大事なんです。繰り返し問題を解いたり練習したり、間違えた内容を誰かに説明したり・・・。何度も何度も繰り返し自分で行動するはずです。そうすることで、やっと少しずつ自分の中に残り始めていくものなんです。そして、それを続けることによって、まだ完璧に理解できていない・身についていないところや、もっと知りたい・上達したいと思えることに出会えるはずなんです。そしてさらに練習を反復する。そのことによって上達していくものなんです。
「おいおい、何を今更当たり前のことを」と思うかもしれませんが、擦り切れるぐらいリピートしてもいいと思えることなので、改めてここに記しておきましょう。
結局、自分が行動することが何よりも大事なのです。むしろ、自分で行動しないと全てが無駄になるんです。
どんなに素敵で素晴らしくわかりやすい先生の説明も、あなたの行動には勝てません。
あなたの行動には、それだけの価値があるのです。
さぁ、どんどん行動して、自身の価値を高めていきましょう。
その行動の先に、あなたが欲しいものが、あなたが叶えたい夢が、待っています。
塾長の独り言・・・
まぁ簡単に言うと、「わかりやすい説明」はあなたの行動を加速させるアイテムみたいなものかな。
ある1日の出来事です!私たち大人の視点を少し変えるだけで、こどもたちは劇的に変化します。
今からお話しする内容は、過去の私の実体験に基づいた話になります。
教室にA君という生徒がいました。彼は、学校の面談でも先生から度々「集中力がない」「いつも手遊びばかりしている」と言われるタイプの生徒で、確かに塾でも注意力散漫でした。
・他の人の物音が気になってしまう。
・他の人への解説が気になってしまう。
・他の人との雑談に入ってきてしまう。
・目の前のことに集中できず作業になってしまう。
・つい筆記用具で遊んでしまう。
教室全体を見まわしているとよく目が合うのがA君でした。顔を上げて、こっちを見てニコニコしている。きっと今までに彼は何度も、いろんなところでこう言われてきたんだろうなぁと想像がつきます。
「集中しなさい!」
僕もついつい言ってしまいそうになります。いや、実際に言ったこともあったかなぁ・・・
そんな私が、「なるほど。集中はしているんだな」と気付いたのは、それからだいぶ経ってからのことでした。
そう、A君も【集中】していないわけではなかったんです。ただ、【集中力】を向けている方向が違うということだったんです。
そもそも大人も子どもも、人間の集中力などというものは何時間も続くものではないですよね。みんな限りある【集中力】をほぼ無意識的に配分して生きているんです。分かりやすく数値化してみましょう。
ある人は自分の持っている100の集中力を、目の前のことに50使い、残りの50は使わずにしまっておく。
いわば、一方方向集中型ってやつです。(ネーミングセンスはお許しください(笑))
さらに別のある人は、集中力を目の前のことに30、残りを周囲に各10ずつくらい向ける。
さらに別のある人は、目の前のことに10、残りを周囲に各20といったように向ける。特に、動きのあるものに注目し、集中力の流動が激しい。
じつはこれ、良いも悪いもない。これらは「集中力の使い方」の違いというだけなのです。
ただ、勉強においては、後者になればなるほど不利に働くということが容易に想像できますね。
もちろん、同じ人でも時と場合によって集中力の使い方は異なります。分かりやすい例を挙げれば、危険を感じるような場所では、誰しも注意力散漫になるのは当たり前です。いろいろなものに注意をする必要があるからです。ちなみに、念のため申し伝えておきますが、当時のA君がいた教室がデンジャラスだったというわけでは決してありませんからね。(笑)
他にも、個人の特性として不安を感じやすかったり、自己肯定感が低かったり、慣れない場所にいるときなどは注意力が分散しがちな傾向がありますね。
それでは、もう一度A君のお話に戻ります。彼は、決して集中していないわけではなく、その方向性が違うだけだったのです。
だから、僕はこう声をかけた。
「集中しなさい!」ではなく、「そんなに集中せんでいいよぉ!」と。
「大丈夫だから。ここは急に発表することもないし、あてられることもないからさ。みんな味方やでぇ!」
「いきなり、何で話聞いてないの?とかみんなの前で間違えるとかないから不安にならなくてOK」
「もうそんなに、周囲の目を気にしなくで大丈夫だからね。」
こういった声かけで、「目の前10、右15、みんなの様子を見て回る私35、左20、近くで生徒に指導している先生20」といった感じのA君の集中力の向きを、「目の前10」だけにしたのです。
効果はテキメンでした。
まずは解くスピードが変わりました。速さだけではありません。正答率も良くなり、授業のテンポが変わったのです。顔は上がらなくなった。目は合わなくなった。少しだけ寂しかった。でも、それ以上に嬉しかった。
いつの間にか当初の10の集中力は、20や30へと膨れ上がり、一点に注がれているなと、見ているこちらも分かるような姿勢になっていました。
A君は変わりました。
現象には理由があって、それを掴み、活かすことが大切だということをA君から教わりました。
ありがとね。
本日3月18日は、【公立高校合格発表日】でしたね!みなさん様々な思いでこの日を待ち望んでいたことでしょう!
私自身も、特に何かができるわけではありませんが、保護者と同じような思いで、ドキドキして生徒からの報告を待ってました。
するとまず第一報がラインで入ってきました。緊張ですぐに見ることが出来ませんでしたが、恐る恐る開いてみると、
【せんせー、合格しまたぁ!!】の文字が入ってました。とにかくうれしかったですねぇ!それ以外表現できません。
そのあとも、電話、ラインで【受かりました!】【合格しました】の連続!!
終わってみれば、全員第一志望校合格の快挙です(@^^)/~~~
当たり前っちゃ当たり前なんですけど、やっぱり嬉しいものです!この瞬間のために生徒、保護者と一緒になって頑張ってきたので!
これを書いている今も、ルンルンで書いてます!この気持ち、表現できません(笑)
生徒や保護者の喜びや、合格を勝ち取るまでの苦労などは、随時アップしていきますので、合格者たちがどのように志望校合格まで歩んできたのか、それを支えてくれた保護者たちはどのように子どもたちと接してきたのかなど参考にしていただければと思います。
とにかく今日は、いいお酒を飲んで、いい眠りにつけそうです!ありがとう、生徒諸君!! 塾長 水田
先日こんなご質問が届きました。
「入試直前のオススメの勉強法について教えてください」
最初は「個々人によって異なるので共通のアドバイス難しいです」と思っていたのですが、散歩しながら、誰もに共通する回答を言語化できるかどうか考えてみました。
至った結論がこちらです。
点数にできそうなところを勉強する!
入試は点取りゲームですから、点数をゲットするための勉強を意識しましょう。すでに点数にできるところはもうやらなくていいですし、なかなか点数にするのが難しそうなところは後回しでいいです。もう残り時間が少ない中で、時間を注ぐのは「点数にできそうなところ」です。
じゃあその点数にできそうなところはどう判断するのかといえば、ヒントをくれるのは過去の自分自身です。過去の模試などを確認して、「どこが点数にできそうか」考えましょう。
またその際に、自分の目標点数も考えておく必要があるでしょう。それによって「点数にできなくちゃいけない範囲」も変わってきますからね。
質問をくれたのは大きな苦手科目がなく、また得意科目もない中央高校を目指す子でした。では、そういう子の立場になって、仮に370点以上を目指してみましょうか。英国70点以上、数学75点以上、理70点以上、社会75点以上、国語80点以上と見立てを立てます。(実際の愛媛県の公立高校入試は50点満点なので、上記の点数の半分の表記になります。ですので、75点を目指す生徒にとっては、39点以上を目指すと言うことになります。)
数学がわかりやすいので、まず数学でやり方を説明しましょう。とりあえずどの層の受検者でも狙いたいのは問1と問2ですね。稀に問2に難易度高い問題が出ますが、なるべく全部狙いたいです。模試や過去問でここが取れていない子は、とにかく問1と問2の練習に時間を使ってください。ここが取れないと、問3以降の問題はとても厳しいです。
さぁ、いよいよ「入試で75点を狙う方法」数学編です。入試で楽する方法じゃないですよ。勉強に苦手意識がある子が、作戦としてどこで点数を取りにいくべきなのかをご紹介していきます。
さて、では数学において上記の目標を立てた子はどうすればいいでしょう。
勝負は、まず取りこぼしを0にすること、ビッグ3の(2)を解けるようにすることです。
まず個人的にビッグ3と呼んでいるのが題問3(規則性)、題問4(関数)、題問5(図形)です。年度により若干の変更はあるものの、大体こんな感じで構成されています。その中でも、各題問の(2)以降の出題に注目します。
その中で点数にできそうなところを考えます。過去問題を解いてみて、題問3~5の中で、どの単元ならまだ取り組めそうかを考えるのです。関数が取り組みやすそうなら、その1点に集中して解きます。
そう、過去問題集の使い方がポイントになるんです。もちろんこうじゃなきゃいけないという決まりがあるわけではありません。あくまで個人的意見ですので、参考になれば嬉しいです。
「関数」が固まってきたら、次は「規則性」、次は「図形」みたいな感じでやっていきます。自分が一番苦手だと思うところは後回しでいいです。直前ですから、点数になりそうなところから攻めていきましょう。また、(3)や(4)は正答率が10%を切るような難しい問題が出題されることもあるので、そこは捨てるという勇気も必要な事もありますよ!
一応他の教科も簡単に説明していきますね。
この直前期は理社国(古典)が伸び時です。時間をかけたいです。暗記科目と言われますが、暗記だけではもちろん解けません。しかし、暗記してなきゃもっと解けません。多くの問題を解いてください。とにかく数をこなしていくんです。そうすれば、同じ回答でもさまざまな問題パターンがあるので、その質問パターンを覚えていってください。いくら考えてもわからないときは、すぐに解答を見てもかまいません。その解答を見て終わり!ではなく、解答と問題をもう一度読み返して、「この質問ではこの回答になるんだな」と問題と解答をセットにして覚えるようにすると、効率よく勉強できます。
一番やってはいけないことが、単語だけ何回も書いて覚えたり、問題集のまとめている部分を読むだけという学習方法です。これではどんな形でテストに出るのかがわかりませんし、自分が何が出来て何が出来ていないかわかりません。いくら勉強をしていても結果が出ないという生徒に多い学習パターンなんです。問題と解答を駆使して、知識を深めることを意識しましょう。上記の数学同様、単元ごとに「点数にできる範囲」を増やしていきましょうね。
なお、どの教科もそうですが、いくら準備をしても、予期せぬことは起こります。でも、安心してください。これだけ情報がある高校入試で予期せぬことが起こったら、それはみんなにとっての予期せぬことですから、(みんなできなくて)合否にはあんまり影響しません。どちらかというと、予期せぬ問題よりそれを見て驚いて手が止まっちゃうことの方が怖いので、予期せぬことは起こると肝に銘じておきましょう。
ここまでかなりマニアックに説明してきてしまいましたが、これらはあくまで個人的意見です。塾に通われている方は、ぜひその塾の先生に相談して言う通りにして下さい。直前はそれが一番です。プロに任せましょう。
また、毎年直前になると守りの勉強(謎の調整)に入る子がいますが、止めてください。学校のテスト前そんなことしないでしょ。前日は早めに寝るとして、それまでは死に物狂いでやっていいですよ。
まだまだ点数伸ばせます。史上最高の努力、ぜひ自分自身に味わせてあげてください。
さぁ、過去最高の自分に出会いにいこう!
本日生徒から、愛媛大学附属高校の『合格』の知らせを受けました!
やったね、〇〇ちゃん!いあぁーホント最高だわ、この瞬間!
しかも、本人は第一希望に上げていた高校だったんですけど、学力的には少し厳しいかなと思っていた高校だけに、喜びも倍増ですね!
保護者様も、「まさか?!番号の見間違えじゃないの?(笑)」的なやり取りで、何度も見直したとのことでしたが、
やはり、合格は合格でした!!
くぅぅぅぅーーー、とにかくうれしいの一言では表現できませんねぇ!
どうしてくれるんだよぉ、この感情!(笑)
とにかくこの喜びの感情を伝えてたくて、みなさんにご紹介しました!
本日多くの中学校が学年末試験の発表となり、来週から学年末試験がスタートしますね。
各学校の試験範囲の用紙も集まってきました。やはり予想通りほぼ全範囲が出題されていますねぇ。
生徒たちには、昨年の冬期講習の段階からこの試験の重要性、範囲の多さ、事前準備でほぼ決まることを伝え、
対策を行ってきました。それでも時間は不足していますが、試験発表が出てからの対策では、よほど普段から勉強している子、もしくは勉強が得意な生徒じゃないと、今までの1学期や2学期の期末試験と同じようにはいかないでしょう。
なんせ、1年間の内容が全て出るわけですからね。1年間の学習を1週間で網羅できるのであれば、受験勉強をする必要ないですもんね(笑)
それでも、何とか抵抗したい、少しでも結果を出したいと後悔している生徒も少なからずいます。
では、そういった生徒たちは何をしたらいいのか!
➀まずは、【しっかり後悔すること】ですね。3学期と言うことは、1学期や2学期の期末試験をすでに経験しているはずです。にもかかわらず、同じ過ちを繰り返していることをまずはきちんと後悔し、反省してください。でなければ、来年も1年間同じ過ちを繰り返し、結果高校入試で後悔することになることはすでに目に見えています。
勉強だけに限らず、何事もまずは何が出来ていないのか、何が不足しているのかなどをしっかりと受け入れることが始まりです。
➁次に、具体的にやることを考えます。多くの生徒たちは一人前に後悔はするんですよね。「もっと早くしとけばよかった」と。ただ、それで終わるんです!理由は簡単!!何をすればいいのかわからないんです。それもそのはず。今までやってないわけですからね。なので水田塾では学習する科目を絞ります。ようは、「二兎を追うもの一兎を得ず」と言うことです。当然全科目大切なわけですから、本来全科目の学習が必要でしょうが、どう考えても無理です!なので、出来る教科、もしくは苦手な教科(生徒レベルによる)に絞る必要があります。
⓷最後に、どのレベルまで学習するのかを決め、解くべき問題を絞ります。当然のごとく応用問題までは手が出せないでしょう。「どの単元のどの内容までは絶対に解けるようにしておく」と言った作業が必要になります。ただこの作業は、テストに出るであろう問題の予測が必要になるため、一人では難しいのです。なので結果的に何もできない、仕方がわからないと言うことになります。ですから当塾では、生徒に必要なレベル内容で対策を実施しているのです。
以上のことは、あくまで定期テストの準備を前もっておこなっていない生徒のことです。本来は最低でも発表がでる1ヶ月前からテストを意識した学習が必要なんです。
今回の試験で後悔している生徒がいるならば、もう一度自分行動を振り返ってみてくださいね!
ただ、今は試験発表中です!無我夢中で我武者羅に勉強しましょう!上記の➀~⓷を意識してくださいね!!
今日私立の受験が終わり、さまざまな表情で生徒全員が報告に来てくれました。
笑顔の生徒、不安そうな生徒、表情が固まっている生徒など、みんないろいろです。
ただ、みんなに共通して言えることは、少しほっとしている様子だったと言うことでしょうか。
やはり受験と言うものは緊張するものです。肉体的な疲労よりも精神的な疲労があったのだなぁと改めて感じたものです。
本来であれば、ここで「ご苦労様」と言ってやりたいのですが、公立高校受験まではあとわずかです。
もう一度気を引き締めて取り組まないと、結局後悔してしまいます。
ここで気を緩めて残りの期間をなぁなぁで過ごしたら、結局今まで何のために頑張ってきたのかわかりませんからね!
ここは厳しく、最後までもう一回やるべきことをやるぞ!!
受験生にとっては本当に大変なことですが、何とか残り1ヶ月弱頑張って、納得のいく結果を出してもらいたいと願っていますし、そのために私自身も、心を鬼にして生徒たちを導いていこうと気を引き締めています。
明日は附属高校の入試、公立高校の推薦入試と、ほんと今週は入試入試の大慌ての一週間です。
私自身も体調管理をしっかりして、生徒たちに迷惑をかけないようにしようと思います。
生徒たちには受験が終わるまでは絶対に直接言いませんが、我慢の限界なのでこの場を借りて一言だけ・・・
「受験生のみんな、昨日今日と本当にお疲れ様!初めての本番の緊張感の中での受験、不安や恐怖もあったと思うけど、よく乗り越えてくれたね!その頑張りは、公立受験にも絶対に役に立つと思うよ!」
やってもやっても成績が上がらない勉強のやり方
「エア勉強」の10の事例と対策まとめ
エア勉強は、やった気にはなるけど成果は出ず、「私は勉強できない」と勘違いしちゃう悪魔の勉強法です。
まずはいくつかその事例をご紹介していきましょう。適宜追加していきます。あえて辛辣に書いているのは、インパクトを強くするためです。ご了承ください。
エア勉強1 何でもかんでも5回書く修行
3回とか10回とか色んなパターンあり。漢字を覚えるために何回か書く(よく中学校の課題にあります)、英単語をただ書くなど、目的があるならまだしも、とにかく書くだけ!覚えているものも無駄に書く。ほとんど勉強時間ではなく作業時間。
エア勉強2 赤ペンで答えだけ書く謎の風習
よくいる。答え合わせの時に、赤ペンで答えを書いて満足しちゃうやつ。赤ペンで答えを書くだけで成績が上がるなら、それはもはや魔術。解いて丸つけまではただのチェック。そこから自分ができていなかったところを「できる」に変える過程こそが真の勉強ということを心に留めておこう。
エア勉強3 できるところばかりやる無双タイプ
できることをやるのは気持ちがいい。それはわかる。しかし、できることをいくらやっても得られる成長は少ないものだ。できないことをできるようにするのが勉強だからだ。もしもあなたが中学生なら、いくら九九を練習してもテストの得点が上がることはないということが想像つくだろう。できるかどうかギリギリラインのことに挑戦しよう。できなかった問題には印をつけて、解説を読み込んだ上で再度挑戦しよう。そこにあなたの成長チャンスが眠っている。
エア勉強4 読めないまま覚える高等技術
英単語や漢字を読めないまま字面で覚えようとする子どもたちが多くがいる。逆に大変で、点数にも成長にもならない。赤ちゃんは、書くことよりも「読む・聞く」ことで日本語を習得していく。読めない言葉をどうやって覚えるのか・・・不思議でならない。
エア勉強5 もはや見にくい七色カラフルノートまとめ
そもそもノートまとめで学力を上げるのは非常に難しい。なるべく問題を解こう。ノートまとめが提出で仕方ないとしても、色ペン使いまくりは時間のロス。テンションは上がるかもしれないけれど学力は上がらない。色はニ色で十分。
エア勉強6 やる気に任せてみる
これはなかなか高度なエア勉強。はじめのうちはやる気を使ってやるのも仕方がない。しかし、それでは続かない。続かない勉強など意味がない。より高いレベルに行きたければ学習習慣・学習計画を利用しよう。
稀に眺めるだけですべて覚えられるという天才がいるが、あなたがそうでないのなら、無理するのはやめよう。紙でも動画でも、ボーッと眺めていたところで時間が過ぎていくだけだ。覚えたいものがあるのなら、愚直にテストを繰り返すのだ。自分自身に負荷をかけなければいけない。
エア勉強8 頭に負荷をかけない見ながら写しゲーム
多くのテストは何かを見ながらは解けない。写すのを練習しても無意味。自分の頭に知識を蓄えよう。筋トレと一緒で、負荷をかけなければ成長などしない。自分の頭に負荷をかけて覚えて、その後問題演習で使い方を確認するべし。
エア勉強9 足の引っ張り合い
「友達と一緒に勉強してくるー」と言って、実際にやるのは難易度が高い。仮にできたとしても、結局一人でやる方が効率的だったりする。友達と一緒なら、遊ぼう。
エア勉強10 勉強の中身じゃなくて眠気と戦う
机に座って、教材を広げて・・・自分自身は夢の中。何も言うことはない。寝なさい。体調管理は自分自身の仕事だ。